

KELK は、熱エネルギーを電気エネルギーに直接変換する「ゼーベック効果」を用いた熱電発電事業を手がけています。そのなかで、熱電発電 EH センサーデバイス製品「KELGEN SD」のプロジェクトを担っているのが熱電発電開発部応用開発グループです。 「究極の IoT 振動センサーデバイス」を掲げる KELGEN SD は、どのようにして生まれたのでしょうか。グループ長の後藤大輔さんと、製品を企画した副グループ長の村田知紀さんに、プロジェクトが走り出したきっかけや、開発途中での苦労、製品に込めた“熱”について語り合ってもらいました。
後藤
KELK は以前から、電気から熱を作り出す「ペルチェ効果」を活用した熱電素子(ペルチェ素子)に関する製品を開発、提供しています。しかし熱電発電事業では、物体の熱エネルギーから電気を作り出す「ゼーベック効果」を用いて製品を開発しています。
村田
私たち二人が開発を担当しているのは「KELGEN SD」と「KELGEN システム」です。KELGEN SD を簡単に説明すると「電池のいらない無線センサーデバイス」ですね。置いた場所と周囲の温度差から発電する熱電変換で動作するので、熱源に置いておくだけでセンシングできます。製品シリーズの中でも、振動センサーデバイスは設置した機械設備などの振動をセンシングして、設備の状態をモニタリングできます。
完全に電池レスで動作し、解析に必要なデータ処理を内蔵することで設備保全を大幅に省力化できるため、「究極の IoT 振動センサーデバイス」を自負しています。実際に、無給電で動作し続ける振動センサーは他社には例がなく、唯一無二の製品といっても過言ではありません。そして、この KELGEN SD をネットワークにつなぎ、センシングデータの測定から収集、解析までを行うソリューションが、KELGEN SD システムです。
後藤
コマツグループの工場や建機をはじめ、数多くの製造業の企業にご利用いただいています。例えば、ある食品製造企業では製造機械の多くが海外産のため、故障した際には海外本社にメンテナンスを依頼しなければなりません。一度故障してしまうと復旧に長い期間がかかってしまうので、可能な限り故障のリスクを低減したいというニーズがありました。
そこで、KELGEN SD を導入し、リアルタイムで製造機械の異常を検知できるようにしています。このように、設備保全に関する効率化や人手不足、技術継承などに課題を抱える企業が現在の主要顧客です。


村田
KELGEN SD の元になるアイデアを発案し、製品化を提案したのは私です。中学の頃から好きな SF 漫画があるんですが、そのなかに“自ら放出した熱を動力源にするロボット”が登場します。それがとても印象的で、子供心に「将来は電池のいらない機械を作りたいなあ」と思って、理系の道を志すことに。その後、大学と大学院で物理学を専攻し、熱電発電事業を扱っていた KELK に入社しました。入社3年目に意を決して、KELGEN SD のアイデアを社内で提案し、試作品の開発や社内レビューなどを経て、2016年に事業化が決定します。その後、プロジェクトが立ち上がり、市場などからフィードバックを受けながら、製品の改善やソリューション化を進めてきました。
村田
KELGEN SD は当初、振動ではなく温度をセンシングする製品でした。しかし、展示会に出品するなどして潜在顧客の意見を聞くと、温度よりも振動をセンシングするほうが圧倒的にニーズがあるとわかったんです。たしかに、機械設備の故障をいち早く検知するには、温度よりも振動のほうが精度は高いです。ただ、振動のセンシングにはかなり多くの CPUの演算量を必要とするため、既存の仕様では消費電力をまかなえません。そこで、新しいデータ解析アルゴリズムを考え、センシングデータの品質と消費電力を調整しながら仕様を詰めていき、最終的に検知性能が違う3種類の製品を販売することになりました。
後藤
現在は、初めて導入いただく企業向けにスターターキットを提供するなどして、製品の販売拡大に力を入れています。今後もさまざまな販売施策を推進し、製品のシェアを広げていきます。なお、プロジェクトの当初は、チームの全員が営業者兼技術者だったんですが、最近は役割分担が進み、村田は本体センサの開発、私はマーケティングや営業を主に担当しています。

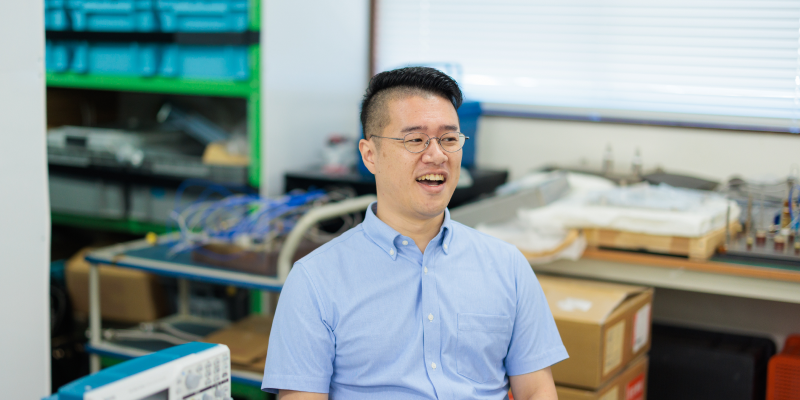
村田
正直なところ、熱くなった瞬間よりも「冷や汗をかいた瞬間」のほうが多いかもしれないです(笑)。
後藤
これまで KELK で取り扱ってこなかった新しい製品なので、ここまでの道のりは試行錯誤の連続でしたから、肝を冷やした場面はかなりありましたね(笑)。
村田
でももちろん、熱くなった瞬間もありますよ。実は、最初に KELGEN SD の構想を社内提案したとき、かなり否定的な意見をもらったんです。「そういった製品が世の中に存在しないのには、理由があるんだ」と。世の中に存在しない製品は誰も思い付かなかったからではなく、誰からも求められなかったり実現が不可能だったりするから存在しない、というわけです。
その言葉にどうしても納得がいかず、熱電発電のスペシャリストである自分たちが使いこなせずして世の中の誰が使えるんだという思いから、翌日からは空いた時間を見つけては、夜中まで試作品を設計する日々が続きました。否定的な意見によって奮い立ったからこそ、KELGEN SD が完成したのかなと思います。
後藤
村田とは逆に、私は今まさに熱くなっている状況かもしれません。元々は技術者でしたが、キャリア30年を越えて初めてマーケティングや販売戦略の仕事をしているので、毎日が新鮮な体験の連続です。年間の3分の1は取引先の工場などに出張し、ユーザーの声や稼働状況をリサーチしています。入社時には考えられないことですね。ただ、製品に関する問い合わせや要望がほとんどなかった立ち上げ当初を思うと、今の仕事に大きな意義が感じられて、やる気がみなぎってきます。


村田
カーボンニュートラルへの貢献も期待されており、製品の導入実績は着実に増えてきているので、今後は製品が継続的に売れる状況をいかに作っていくのかが課題です。そのためにも、顧客の課題をしっかりと見極めて、それに見合うソリューションづくりに注力していきたいと思っています。
後藤
実際にユーザーの声を聞いてみると、顧客の課題は必ずしも技術的なものに限りません。例えば「導入したいけれど、社内で稟議が通らない」といった業務上の課題が壁になっていることがあります。取引先の要望にていねいに対応し、導入を後押ししていきたいです。
後藤
マネージャー兼プレイヤーの立場を続けながら、キャリアを走り抜けるつもりです。このプロジェクトに携わったからこそ得られた経験や学びは、自らの幅を広げ、キャリアを豊かにする上で非常に貴重なものだと思っています。まだまだ目の前の課題は山積みですが、その一つひとつをモチベーションに変えて日々の仕事に向き合っていきたいです。
村田
私は KELGEN SD のプロジェクトを完遂したいと思っています。私が諦めたら、これまでプロジェクトに携わってくれた方々の努力も無駄になってしまうので、責任は重大です。自分のキャリアを代表する仕事にできるよう、製品開発にさらに力を入れていきます。
後藤
もし KELK に興味を持ってくださっているなら、ぜひチャレンジ精神を持って飛び込んできてほしいです。このプロジェクトからもわかるように、KELK には新たな挑戦を奨励して後押しする文化があります。こうした環境のなかで、自らのビジョンを実現したいという方にぜひ仲間になってほしいです。
村田
KELK はものづくりの楽しさを実感できる会社だと思います。時には業務上で苦しい場面もありますが、ものづくりに熱を持って没頭できる環境であることは間違いありません。「新しいものを作りたい」「ものづくりを仕事にしたい」という方なら、とても意義深いキャリアを築けると思います。


 自分が働いているときに発している温度は何度だと思う?
自分が働いているときに発している温度は何度だと思う?後藤
基本的には「平熱」です。熱くなることは大切ですが、仲間や部下に対して熱くなりすぎるのもいけないので、平熱を維持するように心がけています。
村田
私も「平熱」ですが、体温の上下は激しいかもしれません。「マズい!」という事態に、体温が急速に低下する経験を何度も味わっています(笑)。
 プライベートで熱を入れていることは?
プライベートで熱を入れていることは?
後藤
土日はサッカーやサーフィンを楽しんでいます。よいストレス発散になるので、月曜からの仕事にも前向きに取り組めています。
村田
競技ダンスです。妻とのペアで試合に出場しており、シニアの日本代表として世界大会にも出場しています。人前で踊ると舞台度胸がつくので、プレゼンなどの仕事面にもいい影響がありますね。
 KELK らしいイベントや制度は何でしょうか?
KELK らしいイベントや制度は何でしょうか?
後藤
部活動がさかんですね。バドミントン部、マラソン部、釣り部、フットサル部などがあります。最近は、サーキット場でレースを楽しむカート同好会も立ち上がりました。練習頻度や曜日は部活によって異なり、思い思いに活動を楽しんでいるようです。
村田
バドミントン部は、土曜に小学校の体育館を借りて練習し、実力者はコマツ湘南地区のバドミントン部に合流して実業団の選手権大会に出場しています。ここ数年は全日本の大会にもコマを進めていますよ。釣り部は年2回ほど、船を貸し切って皆で釣りに行っているそうです。
